2025年1月31日付けで、社内で新設された生成AI研究開発チームへ配属されました。
3年前、もともとAI関連の技術を触りたいと思い転職したので、ようやく努力が実を結びました。
今回は配属に至るまでの具体的な行動と、今後の発信方針についてお伝えします。
研究開発チーム設立までの道のり
入社当時からAI技術の研究開発に携わりたいという想いはありましたが、当時の組織には専門チームが存在しませんでした。
そこで私は、「資格」、「発信」、「実績」の3つの観点から、会社にAIの必要性を伝える努力をしてきました。
資格取得で技術基盤構築
まずは、AI系(数学含む)の資格を取ってアピールすることにしました。
弊社には資格取得支援制度があり、資格を取ると支援金がもらえるのですが、それのお陰でどの資格を持っているのかが会社に認知されます。
絶好のアピールの場だと思い、会社で定められてる対象資格のうち、数学やAI関連の資格はほとんど取得しました。
- 統計検定 準1級
- 統計検定 データサイエンス発展
- データサイエンス数学ストラテジスト 上級
- AWS Certified Machine Learning – Specialty
- AWS Certified Data Analytics – Specialty
- 統計検定 データサイエンスエキスパート
- 統計検定 統計調査士
- 統計検定 専門統計調査士
- JDLA Generative AI Test 2023 #2
- JDLA Deep Learning for ENGINEER (E資格) 2024#1
これにより会社に、「勤勉な人」、「数学やAIに興味がある人」というイメージを刷り込むことに成功しました。
常日頃の情報発信
全社員が見れるところで、以下のような情報を発信し続けていました。大体週2回~の共有を、1年くらい続けていました。
- 生成AIの最新トピックの共有
- 開発等の業務におけるTips(AI関係ない場合も)
勉強会の開催
この1年、全社向けに勉強会を開催していました。
多いときは月2回、忙しいときは2ヶ月に1回位のペースでした。
内容としては、生成AI関係ない分野が多かったですが、日々情報発信や勉強会の開催で技術に対する意欲をアピールしていました(笑)
情報発信をする人も少ないですが、勉強会を開催する人はほとんどいなかったので、良いアピールになったかと思います。
社外開催のハッカソンへの参加
2つのハッカソンに参加しましたが、どちらも生成AI関連でした。
技術を学ぶのに意欲的なメンバーと、社外のハッカソンに参加してその様子を社内発信したり、実際に作ったものを公開したりと、生成AIってこんな事ができるんだということを社内に周知し、生成AIの便利さ、重要さというものを伝えていました。
結構ウケは良かったです。
アウトプットの重要性
今回の異動が決まった要因は、まさに「継続的な情報発信」に尽きます。資格取得も社内への情報発信も、最初は反響がなくとも、1年も継続していくと確実に信用を積み上げていました。
声に出しても、拾われるとは限らないと思いますが、声に出さないと100%拾われないので、アウトプットは続けててよかったなぁと思いました。
今後のブログの内容
最近、資格は取ってませんので、資格の取得記事は当分アップされないと思います。
これからは、研究開発してくうえで知ったTips等の情報を、ちょくちょく更新していく技術ブログにしていこうかと考えています。
皆様どうぞよろしくお願いいたします。

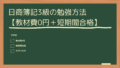
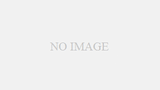
コメント